ハクビシンによる畑の被害対策は?【電気柵が最も効果的】被害を防ぐ5つの具体的な方法を紹介

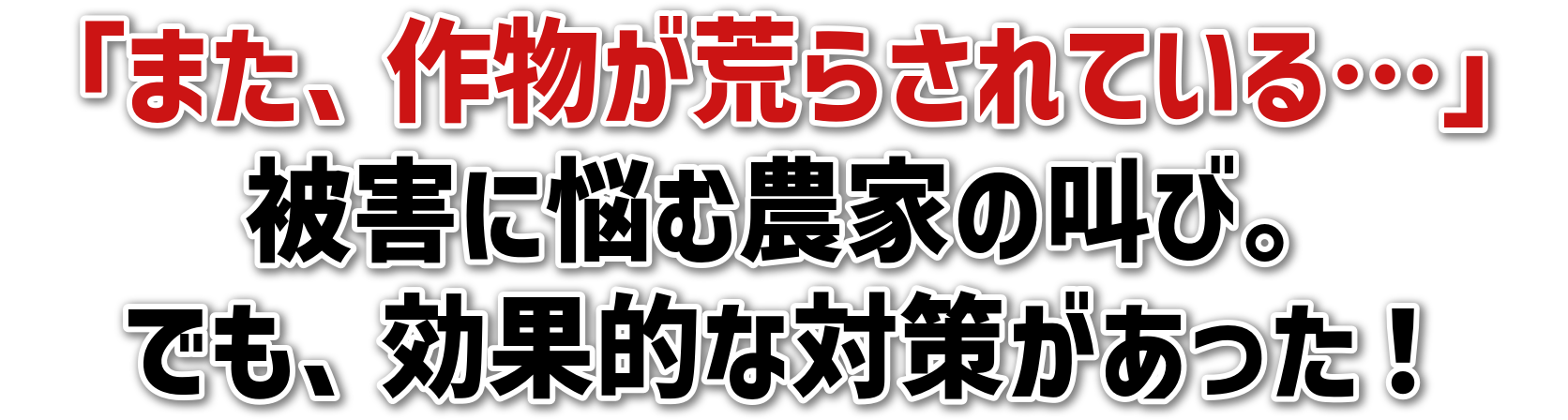
【この記事に書かれてあること】
畑を荒らすハクビシン、その被害に頭を抱えていませんか?- ハクビシンの被害パターンと活動時間帯を把握
- 電気柵の設置が最も効果的な対策方法
- 季節ごとの防御戦略で年間を通じて畑を守る
- ネットフェンスや忌避剤など補完的な対策も重要
- 意外な材料を使った5つの裏技で更なる防衛力アップ
実は、効果的な対策方法がたくさんあるんです。
この記事では、電気柵を中心とした強力な防衛策をご紹介します。
さらに、意外な材料を使った驚きの裏技5選も大公開!
被害パターンの理解から季節別の対策まで、畑を守るための全てがここに。
「もう諦めかけていた…」という方も、この記事を読めば畑を守る自信が湧いてくるはず。
さあ、一緒にハクビシン対策のプロフェッショナルを目指しましょう!
【もくじ】
ハクビシンによる畑の被害対策とは?電気柵の効果を徹底解説

畑を荒らすハクビシンの被害パターン「食害と踏み荒らし」
ハクビシンによる畑の被害は、主に「食害」と「踏み荒らし」の2つのパターンがあります。これらの被害は農作物に深刻なダメージを与え、収穫量を大幅に減らしてしまうのです。
まず、食害について見てみましょう。
ハクビシンは果物や野菜が大好物。
特に甘いものに目がありません。
「うわー、せっかく育てたスイカがぺろりと食べられちゃった!」なんて悲しい経験をした方もいるかもしれません。
トマトやナス、キュウリといった夏野菜も格好の餌食になります。
一方、踏み荒らしの被害も深刻です。
ハクビシンは体重が3〜5キロもあるので、畑を歩き回るだけでも作物を傷つけてしまいます。
「せっかく芽が出たと思ったら、ぺしゃんこ…」なんてことも。
さらに、餌を探して土を掘り起こすので、根菜類も危険にさらされるんです。
ハクビシンの被害パターンには、次のような特徴があります。
- 果実や野菜を丸かじりにする
- 一晩で複数の作物を食い荒らす
- 畝や苗を踏み荒らして歩く
- 餌を探して土を掘り返す
- 作物の茎や葉を折ってしまう
「せっかく手間ひまかけて育てたのに…」と、がっかりしてしまいますよね。
でも大丈夫。
効果的な対策を知れば、ハクビシンから大切な作物を守ることができるんです。
次は、その対策について詳しく見ていきましょう。
ハクビシンの活動時間帯は「夜間から早朝」に要注意!
ハクビシンは主に夜行性の動物です。そのため、畑への被害は夜間から早朝にかけて集中して起こります。
この時間帯が最も警戒が必要なのです。
ハクビシンの活動時間は、だいたい日没後2〜3時間から始まります。
真夜中にかけてどんどん活発になり、明け方まで続くんです。
「えー、そんな時間に見張りなんてできないよ」って思いますよね。
でも、この習性を知ることが対策の第一歩なんです。
具体的な活動パターンを見てみましょう。
- 日没直後:活動を始める
- 夜9時〜11時頃:活動が活発化
- 深夜0時〜3時頃:最も活動が盛ん
- 夜明け前:徐々に活動を終える
「ずるいなー」って思いますよね。
でも、逆に考えれば、この時間帯に焦点を当てて対策を立てればいいんです。
例えば、夜間にセンサーライトを設置するのは効果的です。
ハクビシンは光に敏感なので、突然の明かりにびっくりして逃げ出すんです。
「えいっ!」って感じでしょうか。
また、ラジオを低音量で流すのも良い方法です。
人の声が聞こえると、ハクビシンは警戒して近づきにくくなります。
「人がいるぞ、危ない!」って思うわけです。
夜間の対策は面倒に感じるかもしれません。
でも、「夜中に畑を荒らされるよりはマシ!」と考えれば、頑張れそうじゃありませんか?
ハクビシンの活動時間を知り、その時間帯に合わせた対策を立てることで、被害を大幅に減らすことができるんです。
がんばって夜の畑を守りましょう!
電気柵が最も効果的!「設置高1.5m」で侵入を防止
ハクビシンの畑への侵入を防ぐ最強の味方、それが電気柵です。設置高1.5mの電気柵なら、ほとんどのハクビシンの侵入を防ぐことができます。
これは、多くの農家さんが実証済みの効果的な方法なんです。
電気柵がなぜそんなに効果的なのでしょうか?
それは、ハクビシンの習性と関係があります。
ハクビシンは木登りが得意で、普通のフェンスなら簡単によじ登ってしまいます。
でも、電気柵に触れると「ビリッ」とショックを受けるんです。
「いてっ!」ってな具合に。
一度このショックを経験すると、二度と近づかなくなるんです。
電気柵の設置のコツは以下の通りです。
- 地上から1.5mの高さに設置する
- 柵の下部に隙間を作らない
- 電圧は4000〜6000ボルトに設定
- 柵の周りの草は定期的に刈る
- 雨や雪の日も電圧が落ちないよう管理する
でも大丈夫。
電流量が極めて小さいので、人間が触れても軽いショック程度です。
ハクビシンにとっては十分な威力ですが、人間や大型の家畜には安全なんです。
電気柵の設置は少し手間がかかりますが、その効果は絶大です。
「もう畑が荒らされる心配はない!」って安心感が得られます。
初期費用はかかりますが、長期的に見れば作物を守る最も確実な方法なんです。
ただし、電気柵を設置したからといって油断は禁物。
定期的なメンテナンスが大切です。
「よーし、これで完璧!」なんて思っていると、思わぬところから侵入されちゃうかもしれません。
電圧のチェックや周囲の草刈りなど、こまめな管理を心がけましょう。
そうすれば、ハクビシンから畑を守る強固な砦になるはずです。
ネットフェンスvsハクビシン「隙間4〜5cmで侵入可能」に注意
ネットフェンスはハクビシン対策としてよく使われますが、実は侮れない相手なんです。なんと、わずか4〜5cmの隙間があれば、ハクビシンは侵入できてしまうんです。
「えー!そんな小さな隙間から入れるの?」って驚きますよね。
ハクビシンは体が柔らかく、頭が通れば体も通れてしまいます。
まるで忍者のように、小さな隙間をすり抜けるのが得意なんです。
そのため、ネットフェンスを設置する際は細心の注意が必要です。
効果的なネットフェンスの設置方法は以下の通りです。
- 目の細かいネット(4cm以下)を選ぶ
- 高さは2m以上にする
- 地面との間に隙間を作らない
- 支柱はしっかりと固定する
- 定期的に破損や隙間ができていないかチェックする
ハクビシンは賢い動物なので、ちょっとした隙をついて侵入しようとします。
「ここなら入れそう…」なんて、弱点を探しているんです。
特に注意が必要なのは、地面との接点です。
ハクビシンは掘る能力も持っているので、地面とネットの間に隙間があると、そこから潜り込んでしまいます。
「まるでモグラみたい!」って感じですね。
このため、ネットの下部は地面にしっかりと固定するか、地中に埋め込む必要があります。
また、ネットの継ぎ目や支柱との接合部にも気をつけましょう。
ここに隙間ができやすいんです。
「ちょっとした隙間なら大丈夫だろう」なんて思っていると、そこから侵入されてしまうかもしれません。
定期的な点検も大切です。
台風や強風で破損したり、経年劣化で隙間ができたりすることがあります。
「最初はバッチリだったのに…」なんてことにならないよう、こまめにチェックしましょう。
ネットフェンスは正しく設置・管理すれば、ハクビシン対策として十分な効果を発揮します。
でも、電気柵ほどの効果は期待できません。
予算や状況に応じて、最適な方法を選んでくださいね。
電気柵設置は「やっちゃダメ」!効果を半減させる3つの注意点
電気柵は効果的なハクビシン対策ですが、設置方法を間違えると効果が半減どころか、まったく役に立たなくなってしまうことも。ここでは、電気柵設置時に「やっちゃダメ」な3つのポイントをご紹介します。
これさえ押さえておけば、電気柵の効果を最大限に引き出せますよ。
まず1つ目、「電圧を下げすぎない」こと。
「高すぎると危ないかな…」なんて心配して電圧を下げすぎると、ハクビシンにとっては「チクッ」程度の刺激になってしまいます。
すると、「これくらいなら我慢できるかも」なんて思われちゃって、効果がなくなってしまうんです。
適切な電圧は4000〜6000ボルト。
これくらいあれば、ハクビシンに「もう二度と近づきたくない!」と思わせることができます。
2つ目は、「柵の下に隙間を作らない」こと。
「下の方は大丈夫だろう」なんて油断は禁物。
ハクビシンは賢い動物なので、隙間があれば「ここから入れるかも」と試してみるんです。
地面との隙間は絶対に作らないようにしましょう。
そして3つ目、「柵の周りの草を伸ばしっぱなしにしない」こと。
草が伸びて電線に触れると、電気が逃げてしまい、柵の一部が無効になってしまいます。
「ちょっとくらいなら…」なんて思わず、こまめに草刈りをしましょう。
これらの注意点をまとめると:
- 電圧は4000〜6000ボルトをキープ
- 地面と柵の間に隙間を作らない
- 柵の周りの草は定期的に刈る
でも、これらの点に注意を払うことで、電気柵の効果は劇的に上がるんです。
「よし、完璧な電気柵を作るぞ!」という気持ちで取り組んでみてください。
また、設置後も定期的なメンテナンスを忘れずに。
電圧のチェックや周囲の環境整備を怠ると、せっかくの電気柵も「ただの柵」になってしまいます。
「最初は効いていたのに…」なんてことにならないよう、こまめなケアを心がけましょう。
これらの注意点を守れば、ハクビシンを寄せ付けない強力な防衛線が完成します。
あなたの大切な畑を、ガッチリと守ってくれること間違いなしですよ。
ハクビシン対策の効果を高める!季節別の防御戦略
春の対策は「電気柵の設置と修繕」がカギ!
春はハクビシン対策の本格的なスタートの季節です。この時期に電気柵の設置と修繕をしっかり行うことが、年間を通じての効果的な防御につながります。
まず、冬の間に傷んでしまった電気柵がないか、くまなくチェックしましょう。
「えっ、冬の間に壊れちゃうの?」って思うかもしれませんね。
実は、雪や霜の重みで電線が緩んだり、支柱が傾いたりすることがあるんです。
春の電気柵対策のポイントは以下の通りです:
- 冬の間に緩んだ電線を張り直す
- 傾いた支柱をまっすぐに立て直す
- 錆びた部分がないかチェックし、必要なら交換
- 新しい電気柵を設置する場合は、高さ1.5mを目安に
- 電圧計で適切な電圧(4000〜6000ボルト)を確認
実は、春は畑の周りの環境整備も大切なんです。
冬の間に伸びた草を刈り、見通しをよくしましょう。
ハクビシンは身を隠せる場所があると安心して近づいてくるので、そういった場所をなくすのがポイントです。
また、春は繁殖期の始まりでもあります。
「えっ、もう子育ても始まっちゃうの?」って驚くかもしれません。
そうなんです。
だからこそ、この時期にしっかり対策をしておくことが重要なんです。
春の対策をしっかり行えば、「よし、これで夏の収穫期も安心!」って気持ちで畑仕事に励めます。
ただし、油断は禁物。
季節が変わるごとに新たな対策が必要になるので、次の季節の準備も忘れずにね。
がんばって春の準備を整えましょう!
夏の果実期に備えて「電圧チェックと忌避剤散布」を実施
夏は果実や野菜が豊富になる季節。ハクビシンにとっては「美味しそうな匂いがプンプンするぞ!」という誘惑の季節でもあります。
この時期は特に電圧チェックと忌避剤散布をしっかり行うことが大切です。
まず、電気柵の電圧チェック。
「えっ、春にチェックしたばっかりなのに?」って思うかもしれませんね。
でも、夏は雨が多い季節。
雨で地面が湿ると、電気が逃げやすくなるんです。
だから、こまめなチェックが欠かせません。
夏のハクビシン対策のポイントをまとめると:
- 週1回は電圧計で4000〜6000ボルトを確認
- 雨上がりは特に注意して電圧チェック
- 電線に触れる草がないか確認し、あれば刈り取る
- 忌避剤を定期的に散布(週1回程度)
- 果実や野菜の近くに忌避剤を重点的に散布
「匂いで追い払えるの?」って不思議に思うかもしれません。
実はハクビシンは特定の匂いが苦手なんです。
市販の忌避剤を使うのもいいですが、家庭にあるもので代用することもできます。
例えば、唐辛子やニンニク、酢などをまぜた水溶液を作って散布するのも効果的。
「へー、台所にあるもので作れるんだ!」って驚きますよね。
これらの強い匂いは、ハクビシンの敏感な鼻をくすぐって「ちょっと、この匂いイヤだなぁ」と感じさせるんです。
ただし、忌避剤の効果は永続的ではありません。
雨で流されたり、時間とともに薄くなったりするので、定期的な散布が必要です。
「面倒くさいなぁ」って思うかもしれませんが、大切な作物を守るためと思えば頑張れるはず!
夏は暑いので対策が億劫になりがちですが、この時期こそハクビシンの活動が活発になります。
「暑いから今日はいいや」なんて思っていると、気づいた時には被害が広がっているかも。
こまめな対策で、美味しい夏の収穫を守りましょう!
秋の収穫期vs繁殖期「電気柵の強化と餌場の除去」が重要
秋は収穫の喜びと同時に、ハクビシンとの攻防が激しくなる季節です。この時期は電気柵の強化と餌場の除去が特に重要になります。
なぜなら、秋はハクビシンの第二の繁殖期でもあるんです。
「えっ、春だけじゃないの?」って驚きますよね。
実はハクビシンは年に2回、春と秋に繁殖期を迎えます。
そのため、秋は食欲が旺盛になり、より積極的に餌を探すようになるんです。
秋のハクビシン対策のポイントは以下の通りです:
- 電気柵の電圧を上げる(6000ボルト程度に)
- 落下した果実をこまめに拾い、餌場にしない
- 収穫した野菜くずは畑に放置しない
- コンポストの管理を徹底する
- 夜間の見回りを増やす
「でも、春から使ってるから大丈夫でしょ?」なんて油断は禁物。
秋は葉が落ちて見通しがよくなるため、ハクビシンも大胆になるんです。
電圧を少し上げて、より強力な防御線を作りましょう。
餌場の除去も忘れずに。
落ちた果実や収穫後の野菜くずは、ハクビシンにとっては「わーい、ごちそうだ!」というお誘いみたいなもの。
これらをそのまま放置すると、ハクビシンを呼び寄せてしまいます。
コンポストの管理も大切です。
「え?コンポストまで?」って思うかもしれませんが、実はここもハクビシンの格好の餌場になるんです。
蓋をしっかり閉めるか、周りに電気柵を設置するなどの対策が必要です。
秋は収穫の喜びと同時に、ハクビシンとの戦いも佳境に入ります。
でも、適切な対策を取れば、「よし、今年の収穫は守り切れた!」という達成感を味わえるはず。
がんばって秋の畑を守り抜きましょう!
冬は油断禁物!「餌場の清掃と電気柵の維持管理」を継続
冬になると「さすがに寒いし、ハクビシンも冬眠するでしょ?」なんて思っていませんか?実は大間違い!
ハクビシンは冬眠しないんです。
だから冬でも餌場の清掃と電気柵の維持管理を続けることが大切なんです。
確かに、冬はハクビシンの活動は少し鈍くなります。
でも、食べ物が少なくなる分、人里に近づいてくる傾向があるんです。
「えっ、むしろ冬の方が要注意ってこと?」そうなんです。
だからこそ、油断は禁物なんです。
冬のハクビシン対策のポイントをまとめると:
- 落ち葉や枯れ枝を放置せず、こまめに清掃
- 電気柵の雪や氷の付着をチェック
- 電線が雪の重みで垂れ下がっていないか確認
- 支柱が凍結で傾いていないかチェック
- ゴミ置き場や堆肥場の管理を徹底
落ち葉の山や枯れ枝の下は、虫などの小動物の絶好の隠れ家になります。
これらの小動物を餌にハクビシンがやってくる可能性があるんです。
「へー、そんな連鎖があるんだ!」って驚きますよね。
電気柵の維持管理も重要です。
雪や氷が付着すると、電気が逃げてしまう原因になります。
「ピカピカ光ってるから大丈夫!」なんて思っても、実は効果が半減しているかもしれないんです。
定期的に雪や氷を取り除きましょう。
また、雪の重みで電線が垂れ下がったり、支柱が傾いたりしていないかも要チェック。
これらは春になってから気づくことが多いので、冬のうちにこまめに確認しておくと安心です。
ゴミ置き場や堆肥場の管理も忘れずに。
冬は食べ物が少ないので、ハクビシンはこういった場所を特に狙ってきます。
蓋をしっかり閉めるなど、ちょっとした心がけが大切です。
「冬は寒いから外に出たくないなぁ」なんて思うかもしれません。
でも、この時期のちょっとした対策が、来年の豊かな収穫につながるんです。
寒さに負けず、冬のハクビシン対策も頑張りましょう!
畑を守る!ハクビシン対策の驚きの裏技5選
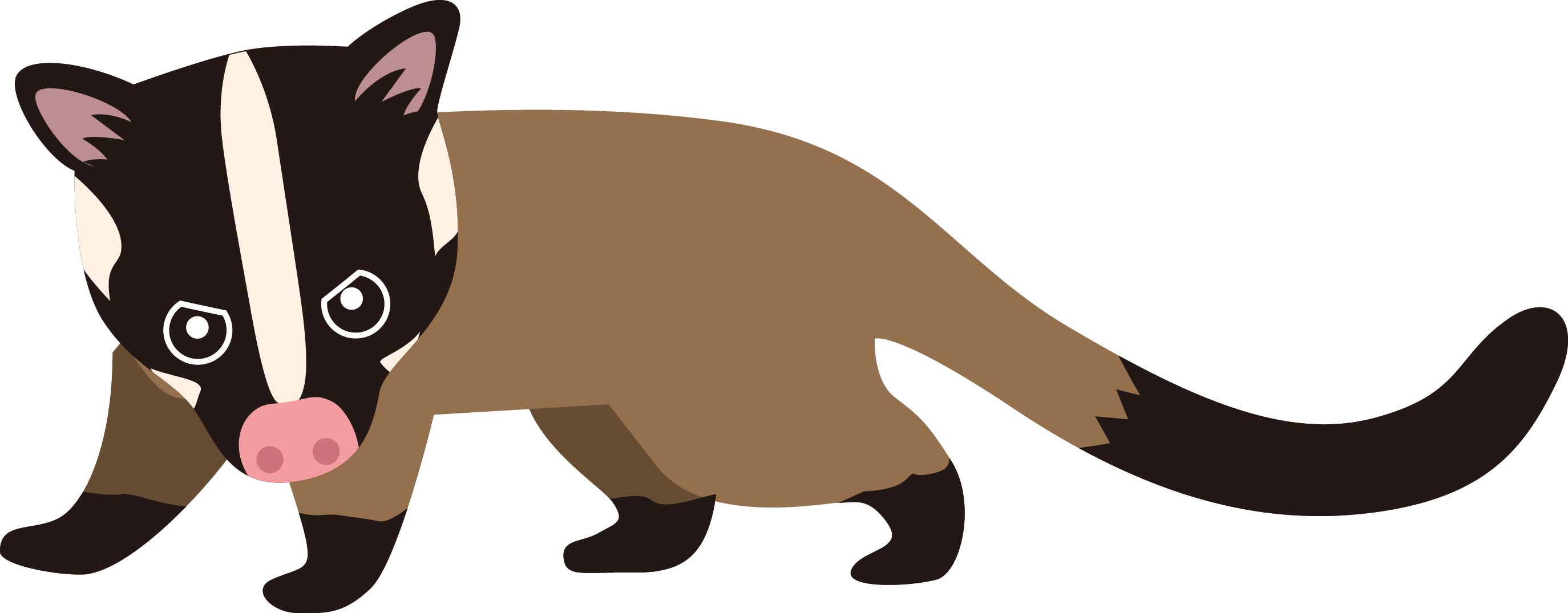
赤いテープの威力!「電気柵周りに巻く」だけで効果アップ
電気柵の周りに赤いテープを巻くだけで、ハクビシン対策の効果がグンと上がります。この意外な裏技、実はとても理にかなっているんです。
なぜ赤いテープが効くのでしょうか?
それは、ハクビシンの視覚特性に関係があります。
ハクビシンは赤色を危険な色として認識する傾向があるんです。
「赤は危ないぞ!」という本能的な警戒心が働くわけです。
赤いテープを使う際のポイントは以下の通りです:
- 幅5cm以上の赤いテープを使用する
- 電気柵の支柱に巻き付ける
- 地面から1メートルくらいの高さに設置
- 10メートルおきくらいに巻くのがおすすめ
- 雨や日光で色あせないよう、定期的に交換する
でも、実際に試した農家さんからは「ビックリするほど被害が減った!」という声が多いんです。
この方法のいいところは、お金があまりかからないこと。
百円ショップでも手に入る赤いテープで十分なんです。
「よーし、今すぐやってみよう!」って気分になりますよね。
ただし、赤いテープだけで完璧というわけではありません。
あくまで電気柵の補助的な役割です。
電気柵自体の管理はしっかり行いつつ、赤いテープでさらに効果アップ!
という感じで使うのがベストです。
ハクビシン対策って、ついお金のかかる方法ばかり考えがちですよね。
でも、こんな身近な材料でも効果があるんです。
畑を守るのに、赤いテープという意外な味方が見つかりましたね。
さあ、あなたも試してみませんか?
スパイシーな防衛線!「唐辛子とニンニク」で侵入を抑制
ハクビシンの嫌いな匂いを利用して、畑への侵入を防ぐ方法があります。その主役は、なんと唐辛子とニンニク!
台所にある身近な食材で、強力な防衛線が作れるんです。
ハクビシンは匂いに敏感な動物です。
特に、刺激的な匂いが苦手。
唐辛子の辛さとニンニクの強い香りは、ハクビシンにとっては「うわっ、くさい!近寄りたくない!」という感じなんです。
この方法の実践ポイントは以下の通りです:
- 唐辛子(一味唐辛子でもOK)とすりおろしニンニクを水で薄める
- スプレーボトルに入れて、畑の周りに吹きかける
- 作物に直接かからないよう注意する
- 雨が降ったら再度散布する
- 週に1〜2回のペースで繰り返す
でも大丈夫、人間にとってはそれほど気にならない程度の匂いです。
ハクビシンの敏感な鼻をくすぐる程度で十分な効果があるんです。
この方法の魅力は、身近な材料で手軽にできること。
「今すぐ始められそう!」って思いませんか?
しかも、唐辛子やニンニクには虫よけの効果もあるので、一石二鳥なんです。
ただし、注意点もあります。
雨で流されやすいので、こまめな散布が必要です。
また、暑い季節は匂いが強くなるので、近所の方に配慮して使用しましょう。
「よーし、今晩のカレーの残り物で早速試してみよう!」なんて思った方もいるかもしれませんね。
身近な食材で畑を守る、なんだかワクワクしてきませんか?
スパイシーな防衛線で、ハクビシンをシャットアウトしましょう!
風船が守る畑!「ゆらゆら動く」姿でハクビシンを威嚇
意外かもしれませんが、風船がハクビシン対策の強い味方になります。風に揺られてゆらゆら動く風船の姿が、ハクビシンを怖がらせる効果があるんです。
なぜ風船が効果的なのでしょうか?
それは、ハクビシンの警戒心の強さにあります。
突然動くものや、正体のわからないものを非常に警戒するんです。
風船のフワフワした動きは、ハクビシンにとっては「うわっ、なんだあれ!怖い!」という存在なんです。
風船を使ったハクビシン対策のポイントは以下の通りです:
- 大きめの風船(直径30cm以上)を使う
- 明るい色や光沢のある風船を選ぶ
- 畑の周りに2〜3メートル間隔で設置
- 地面から1〜1.5メートルの高さにつるす
- 風で飛ばされないよう、しっかり固定する
でも、実際に試した人からは「ウソみたいに被害が減った!」という声が多いんです。
この方法の魅力は、何と言ってもコストが安いこと。
100円ショップで材料が全部そろっちゃいます。
「よし、今すぐやってみよう!」って気分になりませんか?
ただし、注意点もあります。
風船は時間が経つとしぼんでしまうので、定期的な交換が必要です。
また、強風で飛ばされないよう、しっかり固定することも大切です。
「風船で畑を守る?なんだか楽しそう!」って思いませんか?
子どもと一緒に風船を膨らませて、畑の周りに飾るのも素敵な週末の過ごし方かもしれません。
ゆらゆら揺れる風船で、ハクビシンをびっくりさせちゃいましょう!
人の存在をアピール!「使用済み猫砂」で天敵の匂いを演出
意外かもしれませんが、使用済みの猫砂がハクビシン対策に効果的なんです。猫の匂いを嗅ぐと、ハクビシンは「ヤバい!天敵がいる!」と思って近づかなくなるんです。
なぜ猫の匂いがハクビシンを寄せ付けないのでしょうか?
それは、猫がハクビシンの天敵の一つだからです。
野生のハクビシンは、猫科の動物を本能的に恐れるんです。
使用済み猫砂からする匂いは、まさに「ここは危険地帯だぞ!」というサインになるわけです。
この方法のポイントは以下の通りです:
- 使用済み猫砂を小さな布袋に入れる
- 畑の周りに3〜5メートル間隔で配置
- 地面から30〜50センチの高さに吊るす
- 雨に濡れないよう、屋根のある場所に置く
- 2週間ごとに新しいものと交換する
でも、効果を考えれば、それほど気にならなくなるはずです。
実際に試した人からは「ウソみたいに効果があった!」という声が多いんです。
この方法の魅力は、お金があまりかからないこと。
猫を飼っている友達や近所の人に分けてもらえば、ほとんどタダでできちゃいます。
「よーし、早速お願いしてみよう!」って気分になりませんか?
ただし、注意点もあります。
強い匂いが苦手な人もいるので、近所の理解を得ることが大切です。
また、雨で濡れると効果が落ちるので、定期的な交換も忘れずに。
「猫砂で畑を守る?なんだか面白そう!」って思いませんか?
意外な材料でハクビシン対策、やってみる価値ありですよ。
さあ、あなたも猫の力を借りて、畑を守ってみませんか?
光の反射で撃退!「古いCD」を吊るして侵入を防ぐ
もう聴かなくなった古いCD、実はハクビシン対策の強い味方になるんです。CDの表面が反射する光が、ハクビシンを怖がらせる効果があるんです。
なぜCDの反射光がハクビシンを寄せ付けないのでしょうか?
それは、ハクビシンが急な光の変化を非常に警戒するからです。
CDが風で揺れて光を反射すると、ハクビシンにとっては「うわっ、なんだあの光は!怖い!」という感じになるんです。
CDを使ったハクビシン対策のポイントは以下の通りです:
- CDを紐で吊るし、畑の周りに設置
- 2〜3メートル間隔で複数枚配置
- 地面から1〜1.5メートルの高さに吊るす
- 風で自由に回転するよう、ゆるめに固定
- 月に1回程度、表面の汚れを拭き取る
でも、実際に試した人からは「信じられないくらい効果があった!」という声が多いんです。
この方法の魅力は、何と言ってもコストがほとんどかからないこと。
家にある使わなくなったCDで十分です。
「よし、今すぐ押し入れからCD探してこよう!」って気分になりませんか?
ただし、注意点もあります。
強い日差しの下では、CDの反射光が近所に迷惑をかける可能性があります。
設置場所には気を付けましょう。
また、長期間外に置くと劣化するので、定期的な点検と交換も必要です。
「CDで畑を守る?なんだかアート作品みたい!」って思いませんか?
実用的でありながら、ちょっとオシャレな雰囲気も出せるんです。
さあ、あなたも光る守護者たちで、畑を守ってみませんか?
きらきら輝くCDで、ハクビシンを撃退しちゃいましょう!